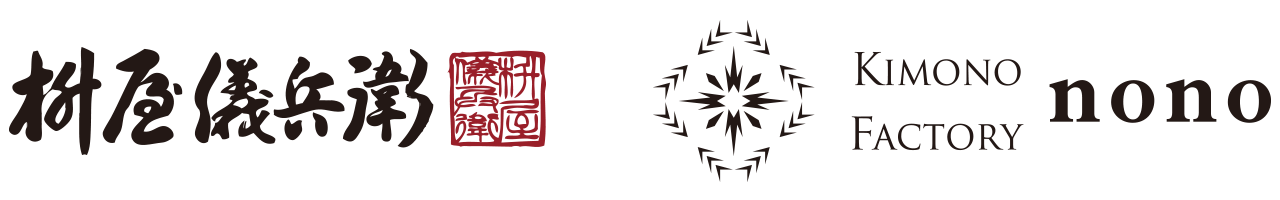ここではメインとなる本場大島紬について簡単にご紹介致します。尚、ここでの製造工程は当社製品を基本にしております。他社商品に関しましては異なる場合もございますのでご了承くださいませ。
本場大島紬 製造工程
1.デザイン原図

細やかな点(絣)で複雑な柄を表現する大島紬。設計前にデザイン画を起こし、柄を決定します。当社では最近まで手書きで行っていました。デザインの段階でマルキや算といった糸や組織の規格も決めます。
2.図案調整

それぞれの柄をどのような点で表現するのかを設計します。点一つ一つの色や大きさなどを含め、方眼紙の中にある制約の中でどれだけデザインを表現できるか、図案師と呼ばれる設計士を中心に検討を重ねて決定していきます。
これ以降、製造工程に入っていくと修正や変更ができなくなります。
3.糊張り(整経)

設計図に基づき、どんな太さの糸を使い、どのような長さで何本必要なのかを計算し、準備します。
絣となる糸については次の工程(締機)で絣づくりを行いやすいように16本(設計による)を糊で固めます。ダマが出来て固まると締機の糸を切ってしまったり、まとめた糸が丸くならないと絣の出来栄えに影響しますので、糊を指で均一に伸ばしながら往復します。固める際の糸の張りや弛みの誤差は絣が合わせに影響し、風合いを左右することもあり気候や糊の加減などが関係する工程です。
4.締機

糊で固めて良く乾かした糸を使い、絣をつくります。絹糸に綿糸で防染しますが、その際に「締機」という機を使った本場大島紬ならではの技法を用います。
経糸に綿糸使い、緯糸に糊で固めた絹糸を使います。綿糸で絹糸を織り込み、織られた部分がその力によって防染されます。次の工程で織り上げたものを染めると織り込まれた部分だけが絣になります。
大島紬の細やかな絣を生み出す工程です。
5.染め(泥染め)

大島紬の代表的な染色方法が泥染めです。枡屋儀兵衛大島紬の多くも泥染めを用います。(一部製品を除く)
はじめにシャリンバイ(車輪梅。テーチ木とも言われる)と呼ばれる木を12時間以上煮込み、煎出液を作ります。その液で糸を20回ほど染めます。糸に染料がしっかり入るように揉み込みながら染めます。
シャリンバイでしっかり染めた後、泥の田んぼで揉み込みます。シャリンバイの染液に含まれている「タンニン酸」と田んぼ内の「鉄分」が化学反応することによって染まります(鉄媒染)。
染色のために揉み込みますが、この工程は泥染め製品の着心地に一役買っていると言われ、生地が柔らかくなる要因の一つと言われています。(揉み込むことで糸がこなれて柔らかくなるとされています。)
尚、一度の染色ではしっかりとした黒になりませんので、これらを何度も繰り返すことで深みのある黒に染まっていきます。(車輪梅20→泥→ 車輪梅20→泥→ 車輪梅20→泥→ 車輪梅20→泥 というふうに染めます)
6.製織

染織が終わり、締機で織り込まれた部分を全て解くと絣が現れます。これらの糸を設計通りに並べて機に立て付け、絣を合わせながら織ることによって柄となります。
緯糸だけでなく、経糸にも絣がある場合は経の絣と緯の絣を合わせながら織らなければなりません。
織りあがったものを見るとこれまでの工程に影響したものが現れる場合もあります。気候や糊の具合、締機、染めを含め、すべての工程途中で影響したもの全てを巧みに調整しながら絣を合わせ、織り上げて完成します。
初めの工程から完成までおおよそ一年の歳月を要します。(製品によって異なります)
nonoサイトではさまざまな形で大島紬を取り扱っております。
大島紬の切り売りもしています。大島紬切り売り
大島紬の小物たちはこちら→大島紬の小物やバッグ