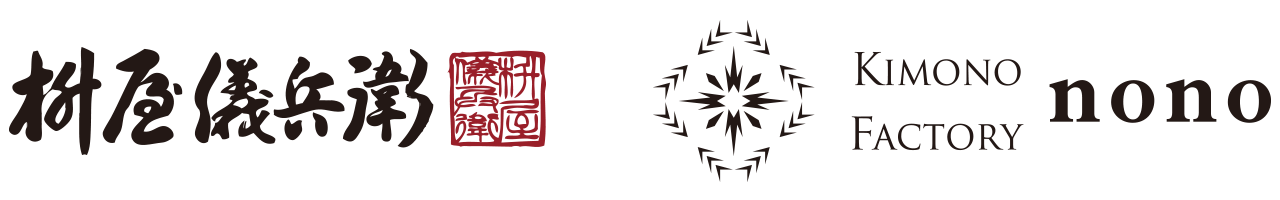大島紬とは
大島紬は、鹿児島県の奄美大島を起源とする絹100%の織物です。糸を先に染めてから織る先染めの平織りで、軽くて滑らか、独特の光沢を持つ風合いが特徴です。
本場大島紬
中でも、「締機(しめばた)」と呼ばれる織機で絣(かすり)を作り、その絣を正確に合わせて織り上げたものが、伝統的工芸品に指定されている「本場大島紬」です。
本場大島紬と本場奄美大島紬の違い
「本場大島紬」は現在、鹿児島県内(一部宮崎県)で生産されていますが、その中でも奄美大島で生産され、「本場奄美大島紬協同組合」の厳格な検査基準をクリアしたものが「本場奄美大島紬」と呼ばれます。
本場奄美大島紬は、伝統的工芸品の検査基準に加え、手織りであることが義務付けられており、「地球印」と呼ばれる特別な証紙が貼られます。
この「地球印」の他にも、本場大島紬には「旗印」(本場大島紬織物協同組合)や「鶴印」(都城絹織物事業協同組合)といった、それぞれの組合が定める基準をクリアしたことを示す証紙があります。
世界三大織物
大島紬は、ゴブラン織やペルシャ絨毯と並んで「世界三大織物」の一つに数えられることがあります。その繊細な技術が評価されています。
大島紬は「紬」なのか?
大島紬という名前から、温かみのある紬糸(つむぎいと)が使われていると想像する方も多いかもしれません。しかし、結論から言うと、現在のほとんどの大島紬は、この紬糸ではなく、生糸(きいと)を使って作られています。
明治時代以前は、繭を真綿にして手で紡ぐ紬糸が実際に使われていました。しかし、大島紬が絣(かすり)の精巧さを極めるにつれて、より細く均一な生糸が使われるようになりました。そのため、現在では、名前だけが当時の名残として「紬」と付いているのです。
用語としての「紬」
現代の着物業界では、「紬」という言葉は二つの意味で使われることがあります。
- 紬糸を使った織物:節のある紬糸を使い、手紡ぎならではの温かみと風合いを持つ織物。
- 先染め織物全体:糸を先に染めてから織り上げる織物の総称。
この観点から見ると、大島紬は糸を先に染めてから織る先染め織物なので、「紬」と呼ぶことができます。しかし、「紬糸を使ったもの」という意味では、「紬ではない」ということになります。
大島紬に関すること
どうして手織り?
本場大島紬の模様は、”絣(かすり)”と呼ばれる「糸につけた点」の集まりでできています。 絣の位置は精密に計算されていますが、気温や湿度で糸が微妙に変化するため、自動織機では柄がずれてしまいます。 そのため、本場大島紬には熟練の職人による手織りが不可欠です。約12mの反物を、絣を正確に合わせながらひと月以上かけて丁寧に織り上げていきます。
絣と締機
大島紬の美しい模様は、絣(かすり)と呼ばれる特殊な技法で作られています。絣は、生地にする絹糸を別の糸で固く縛り、染めることで、縛った部分が白く染め残されることによって生まれます。本場大島紬の場合この作業を「締機(しめばた)」という専用の織機を使って行い、締機で締めた状態の糸は「絣筵(かすりむしろ)」と呼ばれます。
この「締機」を用いることで大島紬の非常に細かく計算された絣配列が可能となりました。本場大島紬の根幹となる技術の一つです。
泥染めと多様な染色
大島紬の代表的な染色技法は、奄美大島に古くから伝わる泥染めです。これは、車輪梅(シャリンバイ)という植物の煮汁と、鉄分を豊富に含む泥を使う技法で、何度も繰り返し染め上げることで、深く美しい黒褐色を生み出します。
泥染めを施した絣筵は、地色が黒褐色になり、絣の部分は白いまま残ります。このほかにも、藍染めや様々な草木染め、さらには化学染料を用いることで、多彩な色合いの大島紬が作られています。
白大島と色大島の秘密
白大島を含め、絣が白いままではなく、色がついている大島紬には、主に「下染(したぞめ)」と「摺り込み(すりこみ)」という2つの技法が使われます。
下染
下染は、糸を染めてから締機で締める技法です。
白大島の場合
糸を黒く染める→締機で締める→脱色する
→絣の部分だけが黒く残り、白地に黒い絣が浮き出る白大島ができます。
泥藍大島の場合
藍色に下染めする→締機で締める→泥染めをする
→絣が藍色、地色が泥染の黒褐色になる泥藍大島ができます。
摺り込み
摺り込みは、白大島と多色使いの大島紬の両方に使われる技法です。染料に浸けるのではなく、スポイト等で筵状態の絣の部分に一滴ずつ色を差していきます。
白大島の場合
白い糸を締機で締めた後、絣の部分に色を差していくことで、カラフルな絣を持つ白大島が完成します。
多色使いの大島紬の場合
泥染めなどで地色を付けた後、白い絣に異なる色を指していくことで、より複雑で豊かな色彩を表現します。
親子三代着られるのか
まれに質問されることがありますが、保存状態と着用頻度によります。決して強靭な生地ではありませんが、筆者は祖父の大島紬を着用しています。ただしその着物は私が着るまでほとんど誰の手も通されていませんでしたし、保存状態も良好でした。
なぜ有名?着物業界の旋風
明治時代に博覧会で人気を博した大島紬でしたが、当時は今と違い一般的な絣の紬だったようです。そこから絣合わせ、締機、高機、糸の変化など様々な創意工夫と開発により現在の大島紬に進化してきました。特に昭和50年前後には伝統的工芸品だけで40万反以上の年間生産があり、大変人気となりました。
最大の特徴である地風、精巧な絣模様、着物を所持する習慣なども影響し、憧れの着物と呼ばれたようです。




本場大島紬の数値「マルキ」
本場大島紬では、「マルキ」や「算(よみ)」といった独自の専門用語が使われています。着物屋さんで「これは〇〇マルキです」と説明された経験がある方もいるかもしれません。
本来、マルキは経糸(たていと)の絣糸(かすりいと)本数を80本で割った数(経糸の絣糸本数 ÷80 本)として、絣の細かさを示す単位でした。しかし、昭和後半頃に「一元絣(ひともとかすり)」から「カタス絣(かたかすり)」が登場したことで、その意味が一変しました。
現在、マルキは「絣の配列(規格)」を示す単位として使われています。例えるなら、織物の「画素数」のようなイメージで捉えると分かりやすいでしょう。
マルキの種類と意味
一般的には、5マルキ、7マルキ、9マルキなどがよく知られています。その他にも12マルキ、8マルキ(13(ジュウサン)9マルキ)、6マルキ(13一元(ジュウサンヒトモト))などと呼ばれるものがあり、これらは糸の密度と絣配列の関係で成り立っています。正式に規定された基準はないため、産地や生産者によって解釈が異なる場合もあります。
また、この規格に当てはまらない特殊な絣配列※1も製造されており、他にも9マルキよりも技術力が必要とされる7マルキなども多く存在します。
そのため、マルキは品質の優劣を表すものではありません。
昔ほど重要視されなくなりましたが、本場大島紬の規格の単位として使われています。
※1 伝統的なものでも割り込み式・亀甲・西郷など様々な配列がある。