 京を歩く
京を歩く 寄稿99 さらに北へ河原町通 / 京を歩く
寄稿者:橋本繁美河原町三条には、かつて京都ロイヤルホテルがあった。結婚式を挙げたところだけに思い出は多い。かつて祇園祭の巡行時、綾傘鉾は棒振り囃子を奉納していた。いまは新しく生まれ変わる建築のためか姿を消している。御池通まで来ると、ゼスト御...
 京を歩く
京を歩く  京を歩く
京を歩く 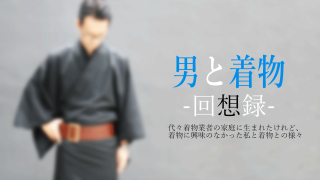 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 - 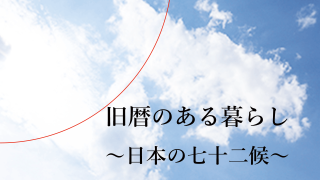 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  京を歩く
京を歩く  京を歩く
京を歩く 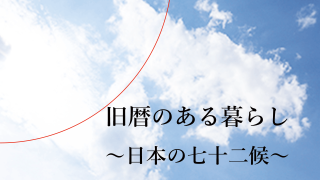 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  京の旬感
京の旬感 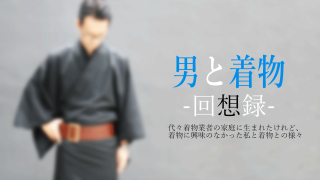 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 -  京を歩く
京を歩く